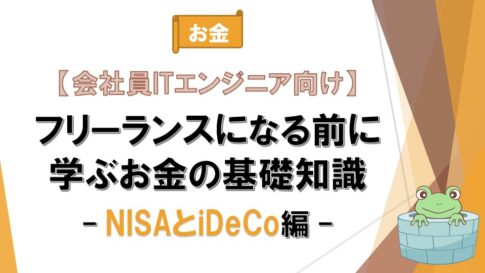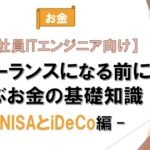「フリーランスになる前に学ぶお金の基礎知識」では、将来的にフリーランスを目指す会社員のITエンジニア向けに、フリーランスになる前に習得すべきお金の基礎知識を厳選してお伝えします。このシリーズを通して、フリーランスとしてつまずくことなく、充実した人生を送るための知識を身に着けていただけると幸いです。

「フリーランスになる前に学ぶお金の基礎知識」シリーズの第11回目である今回のテーマは、「資産運用の必要性」です。今回の講義では、特にフリーランスにとって「資産運用の必要性」が高い理由をわかりやすく解説します。
資産運用とは?

2024年1月から新しいNISAがスタートし、皆さんの周りでも「資産運用」として「投資」を始める方が増えているのではないでしょうか。しかし、周囲の方が始めたからといって、特に考えずにご自身も始めてしまうのは、後々後悔する可能性があります。「資産運用」で失敗しないためには、しっかりとした知識が必要です。
ここで一つお伺いしますが、皆さんは「なぜ資産運用が必要なのか」、きちんと理解されていますでしょうか?

「資産運用が必要性」について答えるためには、「資産形成」と「資産運用」の言葉の定義や、それぞれの関係性をしっかりと理解しておくことが重要です。本章では、これらの言葉の定義とその関係性について詳しく解説していきます。
資産形成

まずは「資産形成」の定義から確認していきましょう。
「資産形成」とは、簡単に言うと「将来のイベントに備えて、必要な資産を築いていくこと」です。例えば、車を買うため、結婚資金を貯めるため、子どもの教育費を計画するため、老後の生活費を準備するためなど、それぞれの人生の目標に合わせて資産をしっかりと築いていくことが「資産形成」です。
資産運用

次に「資産運用」の定義を確認しましょう。
「資産運用」とは、簡単に言うと「手元にある資産を増やすための行為」です。例えば、銀行預金で利息を得たり、株式や債券への投資で利益を得たり、金投資で値上がり益を狙ったり、不動産投資で家賃収入を得るなど、手元のお金を基にして増やす行為が「資産運用」に当たります。
資産形成と資産運用の関係性

ここまでをまとめると、「資産形成」と「資産運用」には上図のような関係性があることがわかります。
「資産形成」は、あるイベントを達成するという「目的」と、そのための「金額」や「時期」などの「目標」を定めることです。そして、その「資産形成」における「目的」や「目標」を達成するための「手段」が「資産運用」ということです。

もう少し詳しく「資産形成」と「資産運用」の関係性について見ていきましょう。
「資産運用」を実際に行うまでのプロセスでは、「目的」、「目標」、「手段」の順番で考えることが非常に重要です。まずは、「資産形成」の「目的」として「どのイベントのために資産を築こうとしているのか」を考えます。次に「目標」として「いつまでにいくら必要か」を明確にします。そして最後に「どのようにお金を準備するのか」を考え、リスクとリターンを踏まえて適切な「手段」を選択します。このようなプロセスを経て、「資産運用」を行うことが正しいアプローチです。

「資産形成」と「資産運用」の定義とその関係性の解説は以上です。
ここまででお伝えしたかったのは、「資産運用には目的や目標が必要だ」という点です。周りに流されて「投資」などの「資産運用」を始める方にありがちなのが、「目的」や「目標」を明確にせずに「投資」を行ってしまうことです。「資産運用」のゴールが明確でないため、途中でリタイアして損失を被ったり、逆に使い道のない「資産」を永遠に増やし続けてしまうこともあります。「目的」や「目標」がないままに闇雲に「資産運用」を行うことは避けるべきです。まずは「何のために資産を形成するのか」を明確にする。そして「いつまでにいくら必要か」という目標を設定し、その上で「どの手段で資産を増やしていくのか」を考える。
このような順番で整理することがとても重要です。
資産運用が必要な4つの理由

ここで、改めて最初の質問に戻ります。「なぜ資産運用が必要なのか」。

その答えを一言で説明すると「時代が変わったから」です。
「資産運用」という言葉に対して、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?実は、「資産運用」は昔と比べて、今の私たちにとって非常に重要な存在になっています。
ご両親から「資産運用」について教育を受けた方は少ないのではないでしょうか。その結果、「資産運用」に対して消極的な見方をしている方も多いかもしれません。確かにご両親の世代では、「資産運用」の必要性がそれほど高くありませんでした。そのため、ご両親の「資産運用」に対する姿勢は間違っているわけではありません。しかし、今は時代が大きく変わり、かつての常識がそのまま通用するわけではないのです。

それでは、なぜ今の私たちにとって「資産運用」がこれほど重要なのでしょうか。その背景には、「低金利」、「税金と社会保険」、「高齢化」、「インフレリスク」という4つの大きな要因が関わっています。これらの4つの要素をしっかり理解することで、資産運用の必要性がより明確になるはずです。
ここからは、30年前の日本と現在の日本で何が変わったのか、これらの要因に基づいて、データを交えながら詳しく解説していきます。
低金利

「今の私たちにとって資産運用が必要な4つの理由」、まず1つ目は「低金利」です。
30年前の日本の金利について、皆さんはご存じでしょうか。実は、当時の日本は現在よりも高金利の環境でした。高金利とは、銀行に預けたお金が自然と増える状態のことを指します。
しかし、現在の日本は、長期にわたる低金利時代に突入しています。この低金利の状況では、銀行にお金を預けてもほとんど増えないということを意味します。30年前と今では、金利においてこのように大きな違いがあるのです。
具体的なデータを使って、この点を確認してみましょう。

こちらは、日本銀行が公表している定期預金金利のデータに基づいて作成したグラフです。このグラフは、1,000万円以上を1年間預けた場合の定期預金金利の推移を示しています。
グラフによると、30年前の定期預金金利は約6%でした。それに対して、現在の定期預金金利はわずか0.03%です。つまり、30年前は100万円を預けて1年後には約6万円増えましたが、今ではたった300円しか増えません。
このデータを見ると、預金だけでお金を増やすのが難しいという現実がはっきりします。

金利を取り巻く状況は、昔と今では大きく変わってしまいました。現在の時代は「銀行にお金を預けてもほとんど増えない」という現実が浮き彫りになっていると思います。そのため、私たちの世代には、単に預金するだけではなく、「資産運用」を通じて賢くお金を増やしていく必要があるのです。
税金と社会保険

「今の私たちにとって資産運用が必要な4つの理由」、2つ目は「税金と社会保険」です。
多くの方がすでに実感していると思いますが、税金と社会保険の負担は年々増加しています。税金や社会保険の負担が増えるということは、つまり、手元に残る使えるお金が減っているということです。
それでは、具体的にどれほど私たちの負担が増えているのか、データを使って確認してみましょう。

こちらは、独立行政法人労働政策研究・研修機構が公開しているデータを基に作成した、税金と社会保険に関する国民負担率のグラフです。
このグラフによると、約30年前は国民負担率が35%程度だったのに対し、現在は45%程度まで増加しており、約10%の右肩上がりで増加していることがわかります。

一方こちらのグラフもご覧ください。こちらは、厚生労働省の労働白書に掲載されているデータを基に作成した、平均給与の推移を示すグラフです。
このグラフを見るとわかるように、約30年前と現在で平均給与はほぼ横ばいであることが確認できます。日本は「失われた30年」とも言われるように、給与はほとんど上がっていません。
給与が増加していないにもかかわらず、税金や社会保険の負担率は上昇しています。
このことから、私たちの手元に残る金額が一方的に減少していると言えます。

要するに、今の時代は、昔よりも自由に使えるお金が減っており、生活が厳しくなっているのです。さらに、今後も税金や社会保険料が増加する可能性が高いため、安心した老後を送るには、しっかりと資産を増やしておく必要があります。こうした状況で、資産運用が果たす役割は非常に大きいのです。
高齢化

「今の私たちにとって資産運用が必要な4つの理由」、3つ目は「高齢化」です。
日本が人口減少や少子高齢化に直面していることは、ほとんどの方がご存じだと思います。このような状況は、先ほども触れたように、税金の増加や社会保険負担の増大など、多くの問題を引き起こしていますが、今回特に注目したいのは「高齢化」です。
それでは、実際のデータを見ていきましょう。

こちらは、国立社会保障・人口問題研究所が公開しているデータに基づいて作成した、平均寿命に関するグラフです。
このグラフは、過去の1950年から未来の2100年までの平均寿命の推移を示しています。1950年時点では、男性の平均寿命が約58歳、女性が約61歳でしたが、2100年には男性が約91歳、女性が約97歳まで上がると予測されています。

つまり、未来の私たちは想像以上に長生きする可能性が高いということです。人が長生きすると、どのような問題が発生するでしょうか?それは、長い寿命に伴って必要とされる費用が増加するという点です。かつての平均寿命を基にした資産形成では、これからの時代において長生きすることで資金が不足する可能性があります。
このような予期せぬ状況でお金が足りなくなるのは、誰もが避けたい事態です。「年金があるから大丈夫」と考えている方もいるかもしれませんが、年金だけでは足りない可能性が高いです。
以前から指摘されている「年金2000万円問題」など、年金だけで生計を立てられる保証はなくなっています。
今は「人生100年時代」とも言われています。しっかりと自分自身で資産を増やし、未来に備えることが、より一層重要になっているのです。
インフレリスク

「今の私たちにとって資産運用が必要な4つの理由」、4つ目は「インフレリスク」です。
皆さんは「インフレ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「インフレ」とは「お金の価値が下がり、モノの価格が上がる現象」です。

「インフレ」について、具体的な例で説明します。ここでは、「ビッグマック」の価格が昔と今でどのくらい違っているのかを見ていきましょう。
2000年ごろ、「ビッグマック」の価格は209円でした。しかし、2024年現在の価格は480円です。「ビッグマック」自体の商品は変わっていないのに、2000年ごろに比べて現在の価格は2倍以上も値上がりしていますね。これが「インフレ」の現象です。
では、この「インフレ」の状態が何を問題としているかというと、「現在のお金の価値が将来下がってしまう」という点です。これが「インフレ」の脅威です。日本は「インフレ」の対極にある「デフレ」の環境が、過去30年近く続いていました。しかし、2023年ごろからはインフレリスクが再燃しているようです。
それでは、実際のデータを確認しましょう。

こちらは、世界経済のネタ帳が掲載しているデータを基に作成したインフレ率に関するグラフです。掲載しているのはG7各国のインフレ率の推移です。
まずは、オレンジ色で示されている日本のインフレ率の推移を見てみましょう。1980年頃の日本は高いインフレ率でした。しかし、1995年ごろから2020年ごろまで、インフレ率は0%近く、もしくはマイナスになる時期もありました。これが日本が約30年近く続いているデフレです。しかし、2022年からは再びインフレ率が上昇する兆しが見られます。このように、今後日本社会がインフレ社会へと移行する可能性が高まっているのです。
また、日本以外の国々のインフレ率にも注目してください。他の国々のインフレ率は、オレンジ色の日本よりも高い傾向が多いことが確認できます。これはつまり、日本の長期にわたるデフレは世界的に見てもイレギュラーな状態であり、世界的にはインフレが標準的な状況であったことが分かります。

ここまでをまとめると、日本は長い間デフレ環境が続いていましたが、今後はインフレになる確率が高くなっています。つまり、将来の出来事に備えて、ただ貯金をしているだけでは、その時にお金を使おうとした際、予想以上にモノの価格が上がっている可能性があり、貯金だけでは足りなくなるかもしれません。そのため、インフレリスクをカバーするためにも、資産運用が必要となるのです。
フリーランスは特に資産運用が必要

「フリーランスにとって資産運用が特に必要な理由」として、会社員とフリーランスの間で決定的に違う点を一つご紹介します。それは、「公的年金制度」です。
多くの方がご存じかと思いますが、会社員は「厚生年金」に、フリーランスは「国民年金」に加入します。「厚生年金」と「国民年金」の違いを簡単に説明すると、厚生年金は保険料が高い反面、受け取れる年金額も多いという特徴があります。

ここで、以前の講義でもご紹介した老齢年金のシミュレーション結果を基に、フリーランスと会社員でどれくらい年金受給額が異なるか見てみましょう。
保険料納付期間を35年、勤続年数を30年、平均年収を500万円と仮定し、年金受給額を計算したところ、老齢基礎年金は71万4千円、老齢厚生年金は82万2千150円が年額で受給できる結果となっています。老齢基礎年金は「国民年金」と「厚生年金」の加入者が受給でき、老齢厚生年金は「厚生年金」加入者のみが受給できる年金であることは、以前の講義でも説明した通りです。

つまり、老後に受給できる年金として、「厚生年金」に加入する会社員は年額約153.6万円受給できるのに対し、「国民年金」に加入するフリーランスは年額約71.4万円受給できるという試算になります。このシミュレーションでは、「厚生年金」と「国民年金」で年額約82.2万円もの差が生じます。
仮に寿命を90歳と仮定すると、65歳から90歳までの期間で、「厚生年金」加入者は約3,840万円、「国民年金」加入者は約1,785万円を受給することになります。その差額は約2千万円にもなります。「国民年金」と「厚生年金」では、これほどの差が生じてしまうのです。
フリーランスにとって、公的年金の観点から見ると会社員に比べて明らかなハンディキャップがあります。この点をしっかりと理解し、会社員以上に老後資金の形成に努める必要があります。そのためにも、「資産運用」は不可欠です。
さいごに
今回の講義はここまでです。今回は「資産運用の必要性」について学びました。次回は「資産運用」の有力な手段である「NISAとiDeCo」について解説します。それではまた次回お会いしましょう。
参考文献
日本銀行 定期預金金利 データコード:IR02’DLDR43TL11Y(預入金額 1千万円以上/1年)※2021年以前
日本銀行 定期預金金利 データコード:IR02’DLDR43TL41YN(預入金額 1千万円以上/1年)※2022年以降
国税庁 民間給与実態統計調査結果 3-1 1年勤続者・1年未満勤続者の給与所得者数・給与額・税額(男、女、合計)
国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(令和5年推計) 詳細結果表 資料表5-4 国連推計による主要国の平均寿命:1950~2100年